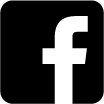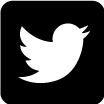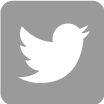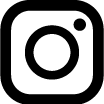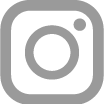TOP > Episode2 Interview
Interview
インタビュー|折田克子 石井漠の「マスク」
石井漠の舞踊映像「グロテスク」と「マスク」について
小松 弘(早稲田大学文学学術院教授・映画史家)
ダニエル彗星の発見者の一人としても知られるアマチュアの天文学者清水真一は、好事家だったようで、若いころは日本に入ってきたばかりのパテベビー撮影機(9.5ミリ幅のフィルムで撮影する映画撮影機)を購入し、多数の動画を撮影している。彼が故郷の静岡県島田市の図書館に自分の撮影した9.5ミリフィルムを寄贈したことによって、われわれは石井漠が振付けた「グロテスク」と「マスク」の一端を現在でも見ることができる。
1922年にフランスで発売されたパテベビーの撮影機・映写機、そしてそれに使われる9.5ミリフィルムは、1923年に初めて日本に輸入された。輸入したのは高島屋飯田株式会社(当時、百貨店高島屋の貿易部門、後の丸紅飯田)である。高島屋はパテベビーの日本総代理店で、震災(1923年9月1日)前は、パテベビーは高島屋でしか買うことができなかった。だが、震災後、当時パリを拠点に活躍していた貿易商の伴野文三郎が銀座にパテベビーを扱う店を開業、さらには老舗の写真機材店浅沼商会もこれを輸入し始め、日本におけるアマチュアの映画カメラマンが1924年から1926年ころにかけて増えていった。1926年には同好の団体東京ベビーシネマ倶楽部が結成され、会員間での情報交換や撮影会が催されることになった。清水真一もこの「倶楽部」の会員であった。1926年10月3日、日本橋の三越の屋上で石井漠の振付による二つの舞踊がアマチュア映画カメラマンたちのために上演されたのは、このような状況のもとにおいてであった。伴野文三郎の伴野商会は9.5ミリ用カメラの販売促進という目的で、同好団体に呼びかけ、朝日新聞社が発行していた週刊グラビア雑誌「アサヒグラフ」の協力の下、1925年に帰国後、築地小劇場などで次々に新作舞踊を発表していた石井漠に協力を依頼した。
伝統的に舞踊家は自分の踊りを映画撮影されることを嫌う傾向にあったが、すでにドイツで「美と力への道」に出演していた石井漠には、アマチュア映画カメラマンの前で舞踊を披露することに何の抵抗もなかったのではなかろうか。また、主催者の側から見ると、映画の主題として舞踊ほど的確に映画の美的側面を補強してくれる対象はなかった。映画はもともと対象の動きを記録するものであって、ダンスはそうした記録を美的な高みにまで押し上げてくれる対象なのだ。だからこそ、19世紀の末に映画が誕生したまさにその時期から、カメラマンはこぞってダンスを映画の主題とした。
「グロテスク」にも「マスク」にもマリー・ウィグマンの舞踊からの影響が顕著に見られるように思うのだが、どうであろうか?「マスク」にはそもそもパがない。支軸は不動で、布で隠され、上半身と、とりわけ腕が表現主義的に動く。石井漠がドイツで何を学んだのか、この映像が物語ることは大きいように思う。
さて、この撮影会では「倶楽部」の何人かの会員が、パテベビーで撮影を行った。清水真一の撮影によるもののほかに、筆者はもう一つ別のカメラマンによる映像の存在を知っている。理論的にはこの撮影会に参加したカメラマンの数だけ映像はあったわけで、これらの舞踊のほかの部分の動きが、そうしたフィルムの中に記録されている可能性は大いにあるということになろう。
折田克子(1936~2018)
舞踊家。石井漠の高弟であり、日本のモダンダンス界を牽引した石井みどり(1913~2008年)を母に持ち、父は作曲家・ヴァイオリニストである折田泉(1908~1972年)。11歳で第一回リサイタルを開催。全国舞踊コンクール文部大臣賞を3度受賞。舞踊家として2003年「紫綬褒章」、2009年「旭日小綬章」など数々の受賞歴を持つ。その活動は国内外にわたり、舞踊界のみにとどまらず広く音楽・演劇界においても展開した。
石井漠(1886-1962)
秋田県山本郡下岩川村に生まれる。
1911年 帝国劇場の歌劇部第1期生に採用され、声楽・日本舞踊・西洋古典バレエ・演技を学ぶ。
1916年 小山内薫・山田耕筰らの新劇場に参加、第1回公演にて石井漠の名で“舞踊詩”を発表する。谷崎潤一郎、佐藤春夫、今東光、東郷青児らと交遊。佐々紅華らと東京歌劇座を結成、浅草日本館を常館に公演し、浅草オペラ・ブームに火をつける
1922年 当時15歳の石井小浪とともに渡欧。ベルリンを皮切りにヨーロッパ各地で公演。「マスク」「囚われたる人」など。映画『美と力への道』(ウーファ社制作)に出演。ドレスデンのダルクローズの研究所で「リトミック」を学ぶ
1925年 帰国。石井漠帰朝第1回舞踊詩公演(東京、築地小劇場)。「法悦」「明暗」ほか。
1938年 石井漠舞踊学校を開校。
1939年 満州公演の際、青島で交通事故にあい、両目の視力が極端に低下する
1948年 終戦後最初の公演後、視力が低下し失明状態となる
1958年 「人間釈迦」上演300回記念公演
1962年 永眠。
インタビュー
語り手 折田克子
聞き手 溝端俊夫
撮影・編集 飯名尚人
協力 石井みどり・折田克子舞踊研究所
挿入映像「マスク」
出演 石井漠
撮影 清水真一
協力 島田市図書館