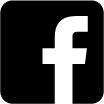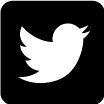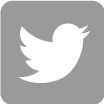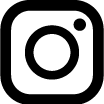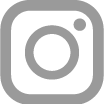TOP > Episode2 Costume
Costume
衣装|大野一雄「花鳥風月」
「花鳥風月」は、1990年にイタリアのクレモナ市立ポンキエリ劇場で初演された。大野慶人演出、大野一雄と慶人が出演する小一時間のダンス作品だ。クレモナは、リュート (バイオリン) 作りで有名な街で、名工ストラディヴァリの工房もここにあった。リュートにちなんだ作品を制作してもらいたいという市の招きに応えて、短期の滞在制作をした。市内のリュート工房を訪ねて、リサーチした。リュート職人は、材料の木を選ぶために森に分け入って、木に素手で触れ、木の声を聴きながら良材を探すのだそうだ。体で自然の声を聞く、というところが日本人の自然観にも通じているというように思い、「花鳥風月」というタイトルになった。花や鳥を登場させたいのではなく、「人と自然」と言うことがテーマだった。アーティストレジデンスが、今のように普通ではなく、まだそういった制作形態の走りで、短い時間だったが、クレモナの柔らかい陰翳に富んだ町並みに迎えられ、静かな、忘れがたい滞在になった。
この衣装の場面では、ドボルザークの「我が母の教えたまいし歌」とシュトラウスの「美しき青きドナウ」を踊る。大野一雄はそれまでの作品であまりバイオリンを使ってないのだが、このドボルザークはバイオリン曲だ。衣装は、「少女の衣装」と呼び習わしていた。
「少女の衣装」というのが、大野作品にはもう一つある、「ラ・アルヘンチーナ頌」の「死と誕生」で使う衣装だ。ふたつの衣装は似ている点がある。頭飾りに白いティッシュをピン留めしている点と洗濯ばさみだ。「花鳥風月」の少女は、長いワンピースの裾を中側に織り込んで膨らみを見せ、前身ごろに洗濯ばさみが四つ五つ、冗談のように着いている。「死と誕生」の少女の衣装は、透けるほど薄い絹が二重になった肌色のワンピースで、ふわふわととても繊細で、着せるのが難しい。そこで衣装係は肩紐の所を洗濯ばさみで押さえて、衣装がこんがらがらないようスタンバイしておくのが常だった。腕を肩紐に通したら、止めの洗濯ばさみを外し、着替えは完了だ。ところがあるとき、着替え終わった大野一雄を舞台に送り出し、気がつくと洗濯ばさみが手元にない。舞台では洗濯ばさみを着けた少女が踊っていた。見事な間違いだが、観客にはどう見えただろうか。「花鳥風月」の衣装作りには、そういった衣装係固有の体験が下敷きになっている。
大野悦子
1938年横浜に生まれる。文化学院美術科卒業。中学生の時に大野慶人と出会い、1962年結婚。1969年、大野慶人の初ソロリサイタル『Dance EXPERIENCEの会』から、大野慶人の衣装を担当する。1977年大野一雄舞踏公演『ラ・アルヘンチーナ頌』以降は、大野一雄の衣装デザインと、着付け、メイクを担当した。
花鳥風月
語り手 大野悦子
聞き手 溝端俊夫
撮影・編集 飯名尚人
協力 大野一雄舞踏研究所